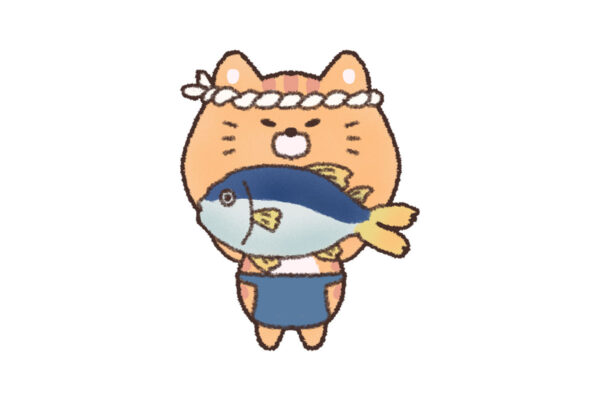カツオを「たたき」にして食べる《納得》の理由とは?薬味たっぷりで5月の体調不良にピッタリ 栄養士ライターが解説
2024.5.15 野村ゆき
カツオの食べ方として、真っ先に思い浮かぶのが、表面を火のついた藁(わら)で炙(あぶ)る「カツオのたたき」ではないでしょうか。カツオのたたきの由来、薬味と食べる理由などを解説します。
「カツオのたたき」の由来は?
 ▲豪快に藁(わら)焼きすることで、食べやすくなり、風味もアップ!
▲豪快に藁(わら)焼きすることで、食べやすくなり、風味もアップ!カツオの食べ方として、真っ先に思い浮かぶのが、表面を火のついた藁(わら)で炙(あぶ)る「カツオのたたき」ではないでしょうか。もともとは土佐の漁師が食べていた“まかない”が一般に広まったとされ、火を通すことで保存効果が高まり、カツオ特有の生臭さが軽減されると考えられています。また、カツオの硬い皮が火に炙られて食べやすくなり、風味が増す相乗効果も。なお、「たたき」の呼び名は、炙ったカツオを厚めの刺身にする際に塩やタレをかけ、手などで軽く叩いて味をなじませたことに由来すると言われています。
なお、カツオにはアミノ酸の一種であるヒスチジンが多く、時間が経ち鮮度が落ちるとヒスタミンというアレルギー物質に変化することも「足が早い(腐りやすい)」と言われる理由の一つとされてます。
カツオのたたきを食べる際に、にんにく、しょうが、大葉(青じそ)、みょうが、ねぎなどの薬味を添えたりトッピングしたりして味わう人も多いのではないでしょうか。カツオと薬味を一緒に食べることにも、おいしいだけではない理由があります。
・強力な薬味の香りが生臭さを消し、食欲を増進させる
・細かく刻むことで細菌の増殖を抑える抗菌作用が高まる
・にんにくに含まれるアリシンがカツオのビタミンB1の吸収を高める
・カツオだけでは不十分な食物繊維やビタミン、ミネラルが補強される
 ▲たっぷり薬味とのマリアージュで栄養効果がアップ
▲たっぷり薬味とのマリアージュで栄養効果がアップ春から初夏へ移り変わる5月ごろは、新年度がスタートし、大きな環境の変化による疲れを感じやすい時期でもあります。薬味たっぷりのカツオのたたきを食べて、心身の栄養補給をしてはいかがでしょうか。
 ▲筆者宅では、辛味が少ない旬の新たまねぎも薬味に加えます!お試しあれ。
▲筆者宅では、辛味が少ない旬の新たまねぎも薬味に加えます!お試しあれ。※参考文献:杉田浩一ほか監修『新版 日本食品大事典』医歯薬出版株式会社,2017、久保田紀久枝・森光康次郎編『食品学-食品成分と機能性-』東京化学同人,2017、藤原昌高著『からだにおいしい 魚の便利帳』高橋書店,2010、レジア編『見て楽しい!読んでおいしい!日本の食材図鑑』新星出版社,2018、農林水産省webサイト
編集ライター歴25年以上。食と栄養への興味が高じて40代で社会人学生となり、栄養士免許と専門フードスペシャリスト(食品流通・サービス)資格を取得。食品・栄養・食文化・食問題に関する情報+好奇心のアンテナをボーダーレスに広げ、分かりやすい記事をモットーに執筆中。
recommend
こちらもおすすめ